 |
|
|
写真1:桜御門跡の石垣 |
|
 |
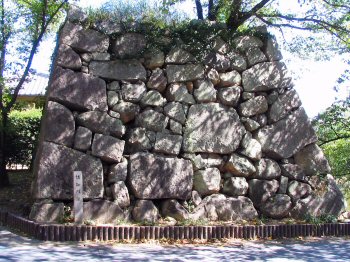 |
|
写真2:追手東隅櫓 |
写真3:鉄御門跡石垣 |
 |
 |
|
写真4:追手門 |
写真5:追手向櫓(御弓櫓) |
 |
 |
|
写真6:天守台登り口 |
写真7:天守台裏側の石垣 |
 |
 |
|
写真8:竹林門跡の石垣 |
写真9:本丸石垣と水堀 |
 |
 |
|
写真10:頬當門跡の石垣 |
写真11:柳御門跡の石垣 |